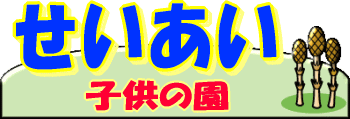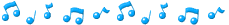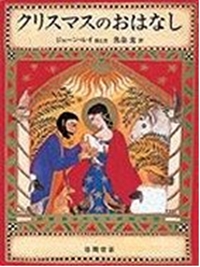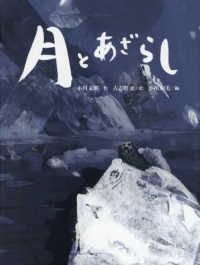2025年も終わろうとしています。
願っていた平和がなかなか実現されない、もどかしく苦しい日々が続く現状も、未だにそのままです。思わぬ災害に見舞われた地域もたくさんありました。復興の遅れも、未だに人々の肩にのしかかったままです。また、ここのところ、熊による被害のニュースが後を絶ちません。つい以前までは、減少していく熊の保護活動などをしていた事実もあったはずだと記憶しています。人間の勝手と言えば、そんな気がしてなりません。気候変動による食物連鎖の崩壊、また人間の手による開発など、様々な原因が探られています。地球全体として、国を超えて、種を超えて、共にそれぞれの暮らしを守るにはどうしたらいいのか、来年に向けても、大きな課題として、継続して考え続けていかねばならないと思います。
ヘロデがユダヤの王であったころ、ナザレのまちに、ひとりのおとめがすんでいました。
なまえをマリアといいます。マリアは大工のヨセフのいいなずけです。あるとき、天のつかいガブリエルがつかわされ、マリアにいいました。「おめでとう、マリア。神の子の母になるのです。男の子を生み、その子はイエスとよばれるでしょう」
マリアはいいました。「おことばのとおりになりましょう。」
ひとつのめいれいがくだされました。くにじゅうの人のかずをかぞえるために、それぞれうまれこきょうにかえれというのです。ヨセフとマリアは、ヨセフの生まれたまち、ベツレヘムへむかいました。ベツレヘムのまちはひとがあふれ、やどやはあいたへやがどこにもありません。やどやのしゅじんはヨセフとマリアをうまやにあんないしました。
マリアはうまやで男の子を生み、ぬのでつつむと、かいばおけにねかせました。かたわらにはウシとロバがいました。
のはらにいたひつじかいたちのまえに、天のつかいがあらわれ、こういいました。「おそれることはありません。うれしいしらせをはこんできたのです。きょうベツレヘムでひとりの子どもが生まれました。そのかたこそが、すくい主、キリストです。あなたがたは、かいばおけのなかのおさな子をみるでしょう。それがしるしです。」
天のつかいがおおぜいあらわれ、神をたたえてうたいました。
「天のたかいところでは、神に栄光がありますように。地にはへいわがみち、すべてのにんげんに、しあわせがあたえられますように」
ひつじかいたちはいまやに、いそぎました。かいばおけのなかにおさな子をみつけて、ひざまずき、おさな子をあがめました。天のつかいのとおりだったので、ひつじかいたちは神をほめたたえながら、いえにかえっていきました。ひがしのくにから、三人のはかせもやってきました。あかるい星がかがやくのを見たからです。「王になられるおさな子はどこでしょうか。ひがしのくにで、そのかたの星をみたのです。」
ヘロデはやっかいなことになったとおもいました。じぶんよりもつよい、あたらしい王が生まれたときいたからです。ヘロデは、はかせたちにいいました。「その子をみつけたら、わたしにおしえてください。わたしもおいわいしたいのです。」しかしほんとうは、ヘロデは子どもをころしてしまおうとかんがえていたのです。
星は、はかせたちをベツレヘムのおさな子のいるうまやまでみちびきました。はかせたちは、おうごん、にゅうこう、もつやくのたからものをさしだして、おさな子をあがめました。はかせたちは、ヘロデのところにはもどってはならないと、神につげられたので、べつのみちをとおってかえっていきました。
ヨセフとマリアと、おさな子イエスはナザレにかえり、おさな子はたくましくそだちました。神がいつもイエスをみまもっていたのです。
12月の絵本はやはり、クリスマスにちなんだものを選んでいます。クリスマスの絵本程、たくさんあるものはないといっていいくらい豊かで賑やかな絵本たちです。何冊も何冊も読みながら、今年の一冊を選ぶ時間は、1年で一番楽しい時間かもしれません。今年は、
何といっても、この絵の美しさと力強さにひかれました。訳者は奥泉光さんです。どこかで聞いたようなと、調べてみると、様々な文学賞を受賞されている小説家さんでした。
巻末に奥泉さんの「あとがき」の言葉があります。一部を引用してお伝えします。
「~イエス・キリストをめぐる物語は福音書とよばれますが、聖書には四つの福音書があります。
それぞれ書いた人の名前をとって、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとよんでいます。
イエスの誕生のお話はこのうちマタイとルカだけにありますが、ジェーン・レイさんは、二つの福音書を自由にむすびつけて、ひとつのお話を作っています。
マリアへの天使のおつげ、うまやでのイエスの誕生、羊飼いの物語、東の国の三人の博士たち、ひとつひとつがなぞめいた魅力にあふれています。
クリスマスの夜、世界のほんのかたすみで起こったちいさなできごと。
それが人類の運命を変えたとすれば、なんと不思議なことでしょうか。」
聖書を知る人も、そうでない人にも物語として、とてもわかりやすく伝わってきます。
ジェーンさんの描く、ヨセフ、マリアをはじめとして、天使、ひつじかい、博士たち、動物たち、星々も、その美しい色遣いや洗練されたデザインがとても、印象的です。
奥泉さんは、謎めいて・・・と表現されていましたが、まるでイコンのような雰囲気がしてきます。
文章もここではかなり割愛してお伝えしています。
ぜひ、奥泉さんの訳としての豊かな言葉も隅々まで味わっていただけたらと思います。
イエス様の誕生は、私たちの日常の中に確かにあったと、実感できるような確かさを、あなたにも伝えてくれるでしょう。
Peace in the world,
Joy to the world,
Happy Merry Christmas to you ! !
(赤鬼こと山﨑祐美子)
戻る
暑い暑いと過ごしてきた夏も、やっと陰りが見えてきたようです。吹く風も、心地よく秋めいてきました。空にはもう入道雲の姿はありません。すじ雲や鰯雲、羊雲が流れていきます。ちゃんと季節は巡ってきています。稲穂も刈り取られ、裸のようになった田んぼにはトンボが舞っています。実りの秋は、私たちの食卓を色とりどりに豊かにしてくれますね。
食べたいものが、すぐ目の前にあるって、ほんとに幸せなことなんです。
たった15つぶの大豆が、一日の食べ物なんて、信じられますか?
80数年前の日本の暮らしを、あの「トットちゃん」が教えてくれました。
トットちゃんが、小学2年生のとき。日本は戦争をはじめました。
戦争をはじめる前は、雨の日が好きだったトットちゃん。それは、夕方にはパパがいるし、犬のロッキーも特別に家の中にいて、みんなあたたかい明るい家にいるからです。
「安心だなあ。うれしいなあ」トットちゃんは幸せでした。
戦争がはじまると、「ねむいし、さむいし、おなかがすいた」が口ぐせになりました。
爆弾をつんだB29という飛行機が飛んでくるたびに、庭につくった防空壕ににげこみました。その大きな穴の中で、いつ爆弾がおちるかとどきどきして、夜も眠ることもできなかったのです。食べるものがなくなってきました。大事な人もいなくなりました。トットちゃんのパパも兵隊さんになって家からいなくなりました。
戦争をはじめる前、トットちゃんのトモエ学園でのお弁当の時間はとてもたのしかったのです。
みんなのお弁当をのぞいては、「海!」と校長先生が言うとき、海のものが足りないお弁当には奥さんがちくわをたしてくれます。
「山!」と言うときは、おいものにっころがしをたしてくれます。なのに、戦争がはじまると、海のもの山のものどころか、食べるものがなくなったのです。
とうとう、トットちゃんの一日の食べものは、だいずが15つぶだけになってしまいました。ママが毎朝、だいずをフライパンで炒って、それをふうとうに入れてトットちゃんにわたします。「これがあなたの一日ぶんのたべものよ。」お弁当が、ふうとうに入った15つぶの豆!「帰ってきても、ほかにないからよーくかんがえてたべるのよ。食べたら、お水をいっぱいのむのよ。豆がふくらんで、おなかいっぱいになるわ」トットちゃんは、学校につくまでに、がまんできなくて、つい3つぶ食べてしまいました。残りは12つぶです。授業中に空襲警報が鳴って、防空壕ににげこみました。お昼になりました。お弁当の代わりに、だいずを3つぶ食べました。残りは9つぶです。まだ、防空壕からでられません。トットちゃんは、だいずをもう2つぶ食べてしまいます。いいや!みんなたべちゃおうかなあ?残った7つぶをみつめます。やっぱり、食べちゃおうかな? トットちゃんは なやみます。
警報解除のサイレンがなりました。「今日はもう帰っていいですよ」と先生がおっしゃいました。トットちゃんは、だいず7つぶを残せました。帰ってからたべるものがあります。
家が近づいてくると、家はあるかな?ママは生きているだろうか?ロッキーは生きているだろうか?ドキドキしながら目をあげます。ああ、みんな生きている!
夕ごはんに、残してきた7つぶの豆をたべました。7つぶでも食べるものがあります。ママもロッキーも生きています。家もあります。トットちゃんは、うれしいのです。
そんな毎日を過ごすうち、トットちゃんは、やせ細っていきました。栄養不良で、からだじゅうおできだらけになりました。そして、東京大空襲でたくさんの人が死にました。東京にすめなくなったトットちゃん一家は青森県に疎開しました。戦争は4年も続きました。
あれから何十年もたち、トットちゃんは今、ユニセフ親善大使として、世界中の恵まれない子供たちを抱きしめています。
今年は、戦後80年という事で、平和を願う絵本がたくさん紹介されています。
トットちゃんこと、黒柳徹子さん。徹子さんは、戦争の話を語り継ぐことをとても大事にされています。
このお話も、何度か話題になったものです。
それが、絵本になって子どもたちに届けられました。
ここにはご紹介しきれませんでしたが、絵本の中にあるキャラメル自販機の話題も戦時中なのに楽しいお話しの一つです。
ぜひ、手に取って読み返してみてください。ちょうど今、NHK朝ドラ再放送で「チョっちゃん」が放映されていますが、徹子さんのお母様、黒柳朝さんのお話しです。
明るく力強くエネルギーに溢れたお母様です。子どもたちを抱え疎開中でも笑顔を絶やさない、そんな姿が徹子さんを彷彿させますね。
この絵本の文章を担当された柏葉幸子さんの言葉にドキッとしました。冒頭に
~トットちゃんが、小学2年生のとき。日本は戦争をはじめました。~
戦争がはじまった~のではなく、はじめました~とは、とても意味深い言葉です。
戦争は、人間が始めなければ、始まらないのです、今世界中起きている戦争も、人間が始めたものです。
だから、戦争を止めるのも人間なのです。私たち日本人は、戦争の被害者であると同時に、加害者であることも決して忘れてはならないことを、改めて実感しました。
加害者であることも決して忘れてはならないことを、改めて実感しました。
巻末にある徹子さんの言葉を添えておきます。
「戦争程、おそろしいものはありません。大好きなお父様は、戦場に行ってしまいます。食べ物はありません。15つぶのだいずが、一日の食べ物です。夜は敵の飛行機が爆弾を落としにくるので、ベッドでは寝られません。庭に掘った穴のなかに、家族でもぐって寝るのです。焼夷弾が空から落ちてきて、町じゅうが燃えるのです。空は真っ赤です。こんなの、イヤですよね。だから、平和でなくてはダメなのです。」
(赤鬼こと山﨑祐美子)
戻る
9月の声を聞くというのに、まだまだ異常な暑さの名残が続いています。
毎年の夏の話題は、年ごとに暑さが増すと記してきましたが、それが現実になってきているような気がします。
~去年よりも暑いよね~というのが、挨拶のように交わされていました。
四季が明確な日本のはずなのに、だんだんぼやけてきていませんか?
本来あるべき姿の地球を人の手で壊し続けているのかもしれません。
積乱雲の重なる空を見上げながら、鰯雲が恋しい気分になってきます。
秋の訪れを心待ちにしていると、月模様が思い浮かんできます。
月は、様々な場面の想いが込められて、絵本の中でも表現されています。
北方の海は、銀色に凍っていました。長い冬の間、太陽はめったにそこへは顔を見せなかったのです。なぜなら、太陽は、陰気なところは、好かなかったからでありました。
一ぴきの親あざらしが、氷山のいただきにうずくまって、ぼんやりとあたりを見まわしていました。そのあざらしは、やさしい心をもったあざらしでありました。秋のはじめに、姿の見えなくなった、自分のいとしい子供のことを忘れずに、毎日あたりを見まわしているのであります。子供を失ったあざらしは、なにを見ても悲しくてなりませんでした。
「どこかで、私のかわいい子供の姿をお見になりませんでしたか。」
いままで、傍若無人に吹いていた暴風は、こうあざらしに問いかけられると、叫びを止めて
「あざらしさん、あなたはいなくなった子供のことを思って、毎日そこにそうして、うずくまっていなさるのですか。・・・私はたいていこのあたりの海の上は、一通りくまなく駆けてみたのですが、あざらしの子供はみませんでした。・・・こんど、よく注意をして見てきてあげましょう。」
「あなたは、ごしんせつなかたです。・・・私の子供が、親を探して泣いていたら、どうか私に知らせてください。どんなところであろうと、氷の山を飛び越して迎えにゆきますから‥‥・。」
あざらしは、目に涙をためていいました。あざらしは、毎日、風の便りを待っていました。しかし、一度約束をしていった風は、いくら待ってももどってはこなかったのでした。
「あの風は、どうしたろう・・・。」・・・・・・・・
こうして、じっとしているうちに、あざらしはいつであったか、月が、自分の体を照らして、
「さびしいか?」
といってくれたことを思い出しました。そのとき、自分は、空を仰いで
「さびしくて、しかたがない!」
といって、月に訴えたのでした。月は、けっして、あざらしのことを忘れはしませんでした。・・・
「さびしいか?」
と、月はやさしくたずねました。
「さびしい!まだ、私の子供はわかりません。」
といって、月に訴えたのであります。
「私は、世の中のどんなところも、みないところはない。遠い国のおもしろい話をきかせようか?」
と月はあざらしにいいました。あざらしは頭を振って
「どうか、私の子供がどこにいるか、教えてください。世界じゅうのことがわかるなら、ほかのことは聞きたくありませんが、私の子供は、今どこにどうしているのか教えてください。」
月に向かって頼みました。月は、この言葉をきくと黙ってしまいました。何と答えていいかわからなかったからです。それほど、世の中には、あざらしばかりでなく、子供をなくしたり、さらわれたり、殺されたり、そのような悲しい事件が、そこここにあって、一つ一つおぼえてはいられなかったからでした。
「おまえは、子供にやさしいから、一倍悲しんでいるのだ。私は、おまえをかわいそうにおもっている。そのうちに、お前をたのしませるものをもってこよう・・・・。」
月は、約束を決して忘れませんでした。ある晩方、南の方の野原で、若い男や女が咲き乱れた花の中で、笛を吹き、太鼓を鳴らして踊っていました。一日のらに出て働いて、月の下でこうして踊り、その日の疲れを忘れるのでありました。月は太鼓が草原の上に投げ出されたのを見て、これをあざらしに持って行ってやろうと思ったのです。月は太鼓をしょって、北の方へ旅をしました。
「さあ、約束のものを持ってきた」
といって、月は太鼓をあざらしにわたしてやりました。あざらしは太鼓がきにいったとみえて、月があたりを照らしたときには、あざらしの鳴らす太鼓の音が、波の間からきこえました。
絵本の表紙を見ただけで、一気に体が冷えてきそうになりました。
「赤い蝋燭と人魚」と言えば、誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。
日本を代表する作家、小川未明の作品です。
様々な月の絵本を探しながら、この作品にたどり着きました。
ここでは、かなり省略して伝えてあります。
ぜひ、手に取ってじっくりと読んでいただきたい作品です。
小川未明の選ぶ言葉の深いところに、魂を揺さぶられる場面が見つかります。
あざらし、月、風、太陽、擬人化された関係が、自然現象の中で生き生きと描かれています。
子を思うあざらしの想いがひしひしと、伝わります。
あざらしとの約束を守り切れなかったのか、守るつもりもなかったのか、風は、あざらしへの思いを持ちながらも通り過ぎていきます。
それに引き換え、月は柔らかく、清々しく、温かく、あざらしを見守り続けます。
今もこんな風に、世界中を見ているのかもしれない、そう思うと、空を仰いで月に願いをかけたくなります。
このあざらしの子供だけでなく、世界中に奪われていく幼い生命のなんと多い現代社会なのかと・・・。
冒頭に、「太陽は陰気なところは好かない・・・」とありました。
上越出身の小川未明にとっては、太陽はそんな存在なのかもしれないと、ちょっと愉快になりました。
月がもたらした太鼓を鳴らすことで寂しさ、悲しさから解き放たれた瞬間があざらしの救いになった、こういう救いは、太鼓でなくとも、誰でも経験があるかもしれません。
巻末に絵を描かれた「古志野実」についての解説があります。
元々はアニメーションであったものを絵本にされたとのこと、力強いタッチが作品全体を覆っています。
今年の十五夜は10月6日だそうです。
ちょっと先走ってしまいましたが、お月見までに、月の絵本に出会ってみるのもいいですね。
(赤鬼こと山﨑祐美子)
戻る